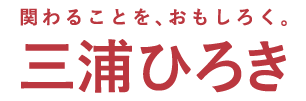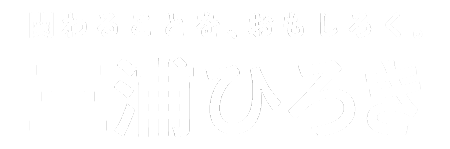【7/29~8/4】
こんにちは、三浦ひろきです。
暑い日が続く中、わずかな曇りの時間を狙って草刈りをしました。
あっというまにボサボサになるこの季節。
スキを見せてはいけませんね・・・。
草刈りの腕はなかなか父に追いつきません。
さて、ここ数回は視察レポートが続いていますが、これで一旦終わりです。
今回は以前より計画していた、台北視察のご報告です。
台湾各地で展開される「社区大学」と呼ばれるコミュニティカレッジがあるのですが、
台北にあるそのいくつかを訪問させていただき、
講義設計や運営方法について、その仕組みをつくられた元台北市政府職員の楊さんをはじめ、
大学運営者の方々にお話を伺いました。

社区とはコミュニティの意味。
社区大学がうまれたのは、台湾の民主化運動の流れによるもので1990年代に遡ります。
限られた人しか行けない大学をもっと多くの人へという考え方から生まれた教育環境整備として設置されました。
また、同時期に「社区営造」という言葉も打ち出され、いわゆる主体的なまちづくり活動が推進されるようにもなりました。
社区大学はその一翼を担っています。
学術や生活芸能だけでなく、地域活動に関わる講義やプロジェクトが数多く開講されています。
浜田でいうと、学校や家庭以外の学び(社会教育活動)を推進する場所としての公民館における各種活動がそれに近いかなと思います。
しかし、大きな違いがありました。
注目したのは、以下の4点。
・収入源をきちんと確保している
・専門的な知識をもった職員が在籍している
・地域へ出て行く職員がいる
・公立小・中・高の空き教室が活用されている(日中も)
台北という大きな都市だからというのはもちろんありますが、受講生が非常に多く、受講料が収入源としてきちんと確保されています。
それは、魅力的な講義がきちんと用意されているからに他なりません。
ニーズ調査はもちろんのこと、先生も審査をクリアしてはじめて着任できるという仕組みは質の担保に直結しています。
学校を開くことで、地域との接続が自然に生まれる設計がされているというのも着目すべき点と言えます。
もちろん、学校側に理解を求める工夫が多々されているのですが、
地域・学校・行政とお互いに補完し合う関係性がきちんとできているように感じました。
社区大学への入学希望者はいまだ増加傾向で、訪れた北投社区大学という小さい規模のものでも3000人。
講義数は150にもなります。
楽しい学び場があるってすばらしい。
事業推進のためには、何事もその基盤となる仕組みが必要です。
住民の主体性向上には社会教育の推進が不可欠であり、効果的と考えています。
現在、浜田市では、自治区制度の解消と合わせ、新しいまちづくりの基盤整備の一つとして、
公民館のコミュニティセンター化が示されています。
コミセン化すれば(機能を強化すれば)万事OKということではなく、そこでどういった事業を動かして行くのか、
使いやすい仕組みを合わせて提案すべきではないでしょうか。
個人的には、この市民大学の設置を今後も提案していきたいと思います。
あっという間に、今週も半ば。
熱中症に気をつけて、すばらしい一週間を!
– 主な日程 –
31日-1日:台北視察(北投社区大学、南港社区大学、楽齢センターなど)
4日:しまことアカデミー