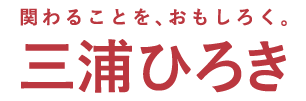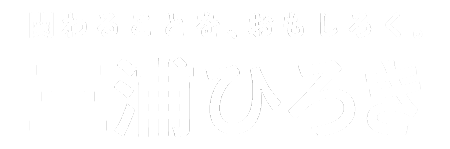【2/9~2/24】
こんにちは、三浦ひろきです。
3月定例会の一般質問を終えました。
今回のテーマは、「水道」。
以前のブログで「水」について触れましたが、その課題感を持って、
市の考え方と水道事業の経営方針について質問しました。

先般、水道事業の経営基盤強化を目的に水道法が改正されました。
コンセッション方式や広域化の推進・・・といった言葉をみなさんも耳にされていると思います。
人口が減れば、使う水の量も減る、つまり料金収入も減るわけですが、
安心安全な水を安定供給するためには、老朽化した施設の更新はじめ、
様々な対応をしていかなくてはなりません。
浜田市の給水人口は52,838人、水道の普及率はほぼ100%。
水道事業は設備投資が大きいです。
人口が減る中で、このカバー率の高いインフラを維持管理していくというのはとても大変かつ難しい。
事実、日本政策投資銀行が、給水人口ごとに水道事業経営を分析したデータをみると、
給水人口が5万人を割ると、料金収入だけでは水道事業は維持できなくなるとあります。
浜田市はぎりぎりです。
このままの経営を続ける限り、安全な水の供給が安定して行えなくなるということ。
言い換えれば、状況を打破する経営改革をして、安定的な水の供給を確保しなければならないということになります。
質問内容と答弁(要約版)はこちら。
*三:三浦、市役所:市
▶︎水の管理について
三:災害時のライフライン確保、衛生管理について「水安全計画」を策定するとあるが未策定。作業を進めるべき。
市:今後策定作業をすすめ、それに基づいて水道管理を行なっていく。
▶︎経営の安定について
三:料金収入が減少、コストカットも限界に近い状況で、新たな収益をつくること(小水力発電など)を検討するべきではないか。
市:土地売却できるものはして、資産管理に努めているが、新規事業開発は未着手。技術開発の動向を注視し研究していく。
三:県で事業を一本化するくらいの広域化が必要ではないか。できることから積極的に検討をすべき。
市:広域化は経営基盤強化のための有力な方策。いきなりの経営統合は難しいが、災害時の相互支援や資材購入などから取り組むのが現実的か。
三:料金激変による市民生活の激変は回避しなくてはならない。基金をあてにしない経営戦略をもつべき。
*今回の料金改定においては市民生活安定化基金が充当されたため、料金改定は段階的になっている(激変回避)。
市:水道事業は独立採算が原則。新設の水道審議会の意見を踏まえながら安定経営に努めたい。
三:サービスに対する適正な料金設定については、激変を避けるための定期的な見直しをすべきではないか。
市:向こう5年間を見越した設定。現状は適正と考えているが、水道審議会において見直しを都度行う。
▶︎有効な広報について
三:小学生の見学時の資料は、学習レベルとあっていない。改善・工夫が必要と考える。
市:説明方法や資料については、すぐに改善に取り組む。
You tubeに近日様子がアップされますので、そちらもぜひご覧ください。
この二週間は、よい勉強もたくさんできたので、
そのことは別号にまとめて書きたいと思います。
そして、今週末は山陰浜田港マリン大橋リレーマラソン。
同僚議員や議会事務局の方々と出場します。
といっても僕は股関節痛がひかず裏方で・・・。
みなさまも、よい週末を!
– 主な日程 –
9日:地域づくりオールスター祭(講師:定住財団主催)
12日:一般質問通告
13日:意見交換(海洋教育について)
14日:社会教育委員の会(傍聴)
18日:議会報告会班長会
19日:本会議(開会、施政方針表明、提案説明)、全員協議会、産業建設委員会
20日:本会議(会派代表質問)
21日:本会議(個人一般質問)
22日:本会議(個人一般質問)、予算委員会質疑通告
23-24日:場づくりについて勉強会・研修