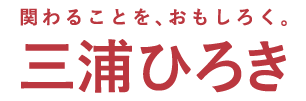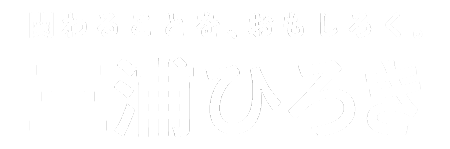こんにちは、三浦ひろきです。
今日は、3月定例会議の質問通告日でした。
今回は会派代表質問もありますので、そちらも共有します。
人口減少社会においては、自らヒト・モノ・コトを生み育てていく力(とりわけ一次産業)と隣人との助け合い(コミュニティ)が何より重要であり、各地域の特色と利点をつなげて相乗効果を生み出し、全体感をもってまちづくりを進めていこうという視点に立って質問項目を考えました。
(1)迅速なコロナ対策について
当面、このような状況が続くと思われる。状況を見ながら、早い対応を引きつづき求めたい。市民の不安に対する正確かつ新鮮な情報提供、また誹謗中傷への対応策も問われるが今後の対応方針はどうか。
(2)特色あるまちづくりについて
自治区制度終了後のまちづくりにおいて、特色あるまちづくりをどのように推進していくか。
(3)社会教育を土台にしたまちづくりについて
これまで公民館を中心にさまざまな活動が実施されてきたが、地域活動を牽引する地域リーダーが十分に足りていない。人づくりが引き続き重要であるが、育成する仕組み、学びの場の提供をどのように行なっていくのか。また、社会教育主事制度がかわり、社会教育士の取得も促すことで、まち全体での社会教育に対する理解促進がはかられると考えるが、これをどのように生かすか。
(4)質の高いまちづくり活動について
公民館がコミュニティセンター化される。市民が主体的に学び、考え、そして行動する拠点として機能するために、まちづくりコーディネーターに大きな期待がある。さまざまな専門知識を有した人材を招聘し、浜田市のシンクタンクとして機能させるべきではないか。また、自治区制度が終了することで、支所や各地域協議会の役割が一層大きくなる。地域活動の単位をどれくらいでみていくか、それによって地域協議会の組織編成も見直しが必要ではないか。
(5)市民参画の機会提供について
次期総合振興計画・総合戦略の策定時期を迎える。前回は100人委員会と称して、市民から意見を集約し共に作る場を設けた。社会教育アドバイザーの長畑先生からは、地域円卓会議の設立についてもご提案をいただいている。また、100人委員会は一度しか開かれなかったこともあり、その後の関係性がとぎれてしまったことをもったいなく思うが、協働のまちづくり推進条例でも市民参画が明確にうたわれており、どう配慮するか。
(6)地域経済の循環について
このような状況下で内需拡大が一層重要である。BUY浜田運動は啓発活動にとどまっている。目標数値とその達成に向けた仕組みの導入が必要ではないか。また、地産地消が農林水産物に限定されている。エネルギーなどを含めた条例の見直しを検討し、そのためにも地産地消率、域外依存率などのポートフォリオを作成し、現状把握につとめるべきではないか。資源を流出させない仕組みとして、飛騨信組の地域通貨、あるいは雲南市での雲南コミュニティ財団などの民間の取り組みもある。参考にしながら、協働で研究してみてはどうか。
(7)一次産業の振興について
自ら生み出す地域産業の重要性が一層見直されている。
①水産業振興(100億の見直し)について
環境の変化もあり漁獲量が減少している。都市部での消費も縮小。漁業関係者を取り巻く状況は非常に厳しい。今後の水産業振興戦略そのものを見直さなくてはならいないと考える。養殖事業や加工事業も含めて、どれほどの事業規模を目標とするのか。水産都市浜田をどのように構築していくか。
②農業・農地の最適化について
集落営農の推進など農業の最適化が重要。弥栄自治区では、13の集落営農が一つになった「弥栄自治区集落営農組織連携協議会」の設立や、一般社団法人奥島根弥栄を核とした、農作業の省力化事業の実践は、県の集落営農のモデルとして位置づけられ評価されている。各地域における小規模農家・農地の最適化推進が必要。また、推奨作物として4つ目にあげられた有機野菜は一つの手法。市外でのブランディングも成功しているがどれくらいのマーケットを捉え、そこをどのように攻略していくのか。県、JA、支援センターの共同体制の再構築も必要と考えるがどうか。
(8)多様な地域産業の支援について
地域社会で活躍する人材を育成し、民間の活力を高めて産業の新陳代謝を進めていく必要がある。起業支援はセミナーだけでなく、江津市のビジネスプランコンテストや福岡市のスタートアップカフェといった仕組みの導入や、起業支援補助制度等の充実も含めた支援体制が必要。また、事業承継も重点課題。地域おこし協力隊制度も活用しているが、対応できる数はわずか。事業体の再編なども踏まえ、地元の雇用維持に注力していていただきたい。産業振興財団等とは棲み分けて、市は何をすべきと考えるか。
(9)ICT社会の実現について
透明性・信頼性の向上、市民協働の推進、経済活性化などを目的に行政データや公共データの公開を積極的に取り組む自治体がある。オープンデータ化することで、まちづくり活動の設計や効果検証の確度向上につながると考えるがどうか。また、教育環境の充実にもICT化の推進は欠かせない。端末配布もされるが、どのような変化がもたらされるか。
(10)定住・交流の促進について
物理的な移動制限がかかる中で、交流方法も変わった。観光ではマイクロツーリズム、働き方ではワーケーション、また、関係人口という域外からの関わり方による新しい活動の創出など、これまで地方の不利な点とされていた「距離」が一般的に縮まった。都会地からのUIターン希望者からの問い合わせも増えていると聞く。この変化に対応した環境整備をどのように講じるか。
(11)公共交通の充実について
金城タクシーの廃業により、地元の方々の移動に大きな影響を与えている。新たな交通財源を持たなければ、地域交通維持は不可能。あわせて市民も利用しなければ地域交通の維持はできない。環境維持、健康維持でマイカー社会からマイカーと公共交通との共生社会への移行も踏まえた再編計画が必要ではないか。
(12)子どもを安心して産み育てる環境づくりについて
不安のない環境づくりが必要である。就学前の支援、結婚支援は追加されたが、子育てはその後が長く、高校までの医療費無料を含めた切れ目のない経済的負担の軽減が重要と考える。また、男性の育児休業取得も重要な課題であり、子育て支援に積極的に取り組む中小企業に対する補助金の創設など、全体的な環境整備が求められる。どのように考えているか。
(13)幼児教育の魅力化と公教育の担保について
子育て世代が重要視する、住みやすい街の条件の一つとして、教育があげられる。公立幼稚園の統合方針も示されているが、ゼロ才からの幼児教育について、これまで明確な位置付けがされていなかった。明確な方針とそれに伴う施設整備がされるべきである。社会教育・家庭教育支援としてふるさと郷育や共育に関する就学前の具体的プログラムの提供により、教育の連続性・一貫性が実現する。組織的アプローチが必要と考えるがどうか。
(14)文化・芸術・スポーツの振興について
浜田市世界子ども美術館へ歴史文化保存展示施設との並存案が示されているが、今後も芸術文化振興の拠点と位置づけ、これまでの活動の量・質ともに損なわれることがあってはならないと訴えてきた。しかし、検討委員会の議論において、その点が十分に議論されていない。これをどう整理していくか。また、今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催予定。地域スポーツはまちづくりの観点からも重要であるが、浜田市におけるスポーツ施策の位置付けが低く、支援も乏しい。今後の振興策をどのように考えているか。
(15)戦略的な介護予防について
三隅ではリハビリテーションカレッジと連携した認知症予防運動や口腔ケアなど介護予防の取り組みが行われている。浜田市全体へ拡充ができないか。官民で戦略的に取り組んで、認定率を下げる努力が必要である。
(16)環境への配慮について
浜田市地球温暖化対策実行計画区域施策編と事務事業編の二つの計画を策定されているにもかかわらず、全体で推進していく意識が低い。子育て支援センターの建設については、計画段階において配慮が十分にされたとは言い難い説明がなされた。自然エネルギーについてはガイドラインの作成がされ一歩前進したが、国の補助も使いながら、長い目でみた施設更新が必要と考える。今後の全庁的な意識醸成、またそれを実行していく仕組みとして、CO2削減量を金額に置き換えて効果を図る取り組みはどの程度すすんでいるのか。
(17)誰もが住みやすい地域風土について
暮らしづらさ、働きづらさを感じておられる方々やそのご家族と社会をつなげる役割が行政に求められている。あさひ社会復帰促進センターのある旭自治区では、受刑者の方々への地域での受け入れやサポートを丁寧に考える風土が醸成されている。暮らしやすいまちをつくるためには地域住民との連携、あるいは雇用の創出や産業イノベーションのためには企業との連携といったように様々な接点づくりと対話が求められる。価値観などの多様性を受け入れ、広く人材を活用していくための戦略をどう考えているか。
(18)公共経営について
経営的視点に立った行財政改革の推進が求められている。特に民間の優れた経営手法、あるいは民間活力を積極的に取り入れる仕組み(PFIやSIB)を用いることによって、新たな財源を生み出すことへの意識が一層必要と考えるが、公共経営をどのように考えるか。
(19)政治信念について
コロナ禍において、政治リーダーに対する信頼が一層求められている。市長の政治姿勢を改めて伺う。
以上
私の一般質問は、保健・医療・福祉事業によるコミュニティづくりをテーマにしました。
高齢化・人口減少が進み、地域コミュニティという社会基盤が弱まっており、その人らしい生活を送ることができる社会の実現には、孤立しないこと(つながり)が重要であり、関係の構築にはテーマや人材等が必要になってくると考えています。
今回は、市民共通のテーマでありながら、普段は意識しにくい「健康」に着目し、コミュニティづくりにおける保健・医療・福祉分野のアプローチについて、質問したいと思います。
(1)保健・医療・福祉事業によるコミュニティづくりについて
①コミュニティづくりにおける保健・医療・福祉的アプローチをどのように捉えているか。
②コロナ禍に、社会とのつながりの回復を求める傾向が強くなったのではないか。その状況は。
③地域包括ケア(病院と施設の医療介護連携)だけではカバーしきれない領域がこれから増えると考えるが、そこをカバーする人材(保健師、保健委員など)や体制は十分であると考えるか。
④今後、まちづくりセンターに求める役割において、社会福祉をどのように位置付けているか。
以上
会派代表質問は、25日の朝一番。
私の一般質問は、26日の午後から(5番目)です。
ケーブルテレビでも放映されますので、ぜひご覧ください。