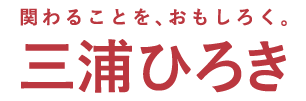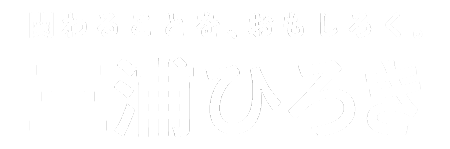【6/29〜7/31】
おはようございます、三浦ひろきです。
あっという間に梅雨明け。
溶けるような暑さの中、アブの猛襲。
夏休みの様相を感じながら、毎日を過ごしています。
定例会議の間は、大事なインプットの時期でもあります。
会派視察、福祉環境委員会視察、会派勉強会などの所管を記します。
(会派視察)
▶︎常石ともに学園
異年齢で編成されたグループで活動するイエナプラン教育の手法を採用している公立小学校。
日々の様子から学習の意義をこどもたちが実感していると感じることができると先生方。
学習指導要領に記された主体的・協働的な学びの実践手法として大変興味深いものでした。
手法にとらわれず、子供たちがよりよい人生を歩めるような機会提供が必要です。
また、職員室のフリーアドレスは、コミュニケーションを促すのに効果的だと思います。
▶︎まちと学びのイノベーション研究所
スマートシティを目指す真庭市での取り組み。
人が減る中、テクノロジーの活用でスマート化していく考え方は強く持つべきと思います。
スーパーアプリの導入は市民サービス向上に有効だと率直に感じました。
かねてより導入の有効性を唱えているデジタル地域通貨の導入はその一つで、医療、福祉、防災、地域交通など、あらゆる分野でサービス向上が期待されますから、大きなプラットフォーム導入の構想をまずは描くべきですね。
▶︎真庭あぐりガーデン
循環型社会をテーマに作られた民間の施設。
テーマに関心がある人や共感している人の関わの形が、ここを拠点に実践されていました。
参加型の運営がコミュニティ形成に強く働いています。
浜田では、三ツ桜酒造跡地の賑わい創出を目的とした利活用が検討されていますが、何を持って賑わいを創出するのか、コミュニティ形成をしていくのか、そのテーマ設定は十分に行われるべきだと思います。
(委員会視察)
▶︎福岡地域戦略推進協議会
官民連携による社会課題解決のための投資スキーム、ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB = Social Impact Bond)について学びました。
その仕組みを用いて実践されたフレイル予防やがん検診率アップの取り組みからは可能性を強く感じました。
地域コミュニティ活性化、市民の健康づくり、地域経済活性化、地域の賑わいづくりなど多面的な効果を期待することができる点が魅力的です。
一方で、事業を作っていく上で、特に初動のサポートをする事業体は欠かせないと感じました。
▶︎ROREN
デイサービスに通われている方々が素晴らしいアート作品を作られています。
誰がそれをやったのかは付加価値であって、社会が必要とするアウトプットにつなげていく(社会との関係性を作る)ことを重要視しているとのこと。
利用者の方々の社会参加にとって最適なアプローチだと思います。
現場での負担は増えても、サービス提供者がやるべき姿を問いかけ続けて理解を得てきたというプロセスを伺い感銘を受けました。
▶︎日置市
キャッチコピーは、コツコツ(Co2Co2)取り組む。
環境変化が深刻になることを踏まえ、資源活用に熱心に取り組まれている自治体でした。
市内各所にバケツを設置して、生ゴミ回収を行っておられます。
50世帯からスタートした取り組みが、現在は14000世帯へ大幅に増加。
負担が増えることでも市民の理解が浸透してきている証です。
副産物として出る堆肥がJAS認証というのにも驚きました。
▶︎大崎町
こちらは、リサイクル率日本一のまち。
徹底した分別と埋め立ての手法によって、焼却炉を持たずゴミ処理をされています。
大きなコストがかかる焼却炉の建設を目の当たりにして、町民と重ねられた協議は450回。
捨てればゴミ、分ければ資源。
浜田市における資源ゴミの利活用やリサイクル方法、ゴミの分別方法も改めて考えてみる必要がありそうです。
(会派勉強会)
▶︎小さな拠点ネットワーク研究所
様々なところで耳にするDX。
ICTプラットフォームを活用した情報共有やデータ分析の具体事例を伺い、負担軽減、地域の見える化、コミュニケーションの活発化において大きな費用対効果を感じました。
旭町和田地区の地域運営組織(RMO = Region Management Organization)でも導入が実験的に行われ始めたとのことで注目です。
以上
有意義な視察・勉強会でした。
浜田の今と照らし合わせながら、最適な施策を研究していきます。
よい週末を!
– 主な日程 –
1日:江津市波子町勉強会(講師)
3-4日:会派視察
7日:しまコトアカデミー説明会(メンター)
10日:議会改革推進特別委員会
22-24日:福祉環境委員会視察
26日:会派勉強会